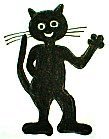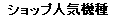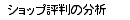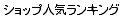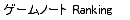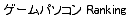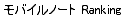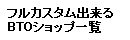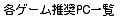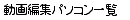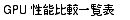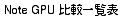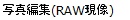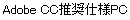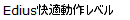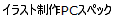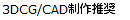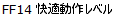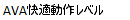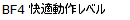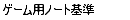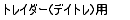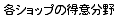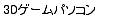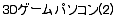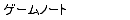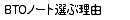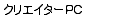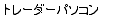初心者にやさしいハードディスク知識;S−ATA、S−ATA2
(本ページはプロモーションが含まれています)
BTOパソコンのハードディスクは、自分の用途に見合った容量(サイズ)を選べばよいのですが、今の新しいPCですと、だいたい160〜320GB程度を選ぶ方が多いようです。
1月末発売の新しいOS:Windows Vista になりますと、Home Basic 版で、20GB以上、Home Premium, Business, Ultimate 版ですと、40GB以上がマイクロソフトの推奨となります。
さて、本ページは、シリアル−ATA(S−ATA)タイプのハードディスク解説です。
![]() アマゾンで内蔵ハードディスクの価格を調べる
アマゾンで内蔵ハードディスクの価格を調べる。
【 S−ATA 】:
現在の主流ハードディスクは、このS−ATA(シリアルATA)に移ったため、従来のATA方式をパラレルATA(P-ATA)と言って区別することがあります。
S−ATA方式は、従来のATAの内部転送速度が速くなり、ATA133:133MB/秒のパラレル伝送方式の限界に近ずいたため、シリアルに変える必要があり、規格として登場しました。
問題というのは、パラレルデータを、ストローブ信号で、同期転送するには、各データ間の遅延時間が異なり同期できなくなったということです。(これをクロック・スキューの問題ということがあります。)
新S−ATA(シリアルATA)方式は、差動(ディファレンシャル)方式の回路を採用して、耐ノイズ性を上げています。また、1ビット伝送であるため、遅延時間が異なり同期できないということはありません。
S−ATA(シリアルATA)方式の接続部は、接続ピン数が、7ピン信号と15ピン電源線から構成されています。また、接続できるケーブル長は、1m(従来の2倍)と言われています。
この7ピン信号の内訳は、アップロード(上り)差動対2本、ダウンロード(下り)差動対2本の信号と3本のGND信号から構成されます。
また、モーター回転数は、7200/10000回転(RPM) 、内部メモリーバッファも8/16MBの2種があり、いずれも大きい方が高速HDDということになります。
S−ATAは、その外部転送速度の違いによって、S−ATA1とS−ATA2に分類されます。S−ATAは、その総称といえます。
S−ATA1方式:外部転送速度:1500Mbit/s(1.5Gbps)、ATA150(150MB/s)、動作周波数:1.5GHz
S−ATA2方式:外部転送速度:3000Mbit/s(3.0Gbps)、ATA300(300MB/s)、動作周波数:3.0GHz
ここで、解かりにくい転送速度、ATA150、やATA300、の表現形式ですが、S−ATA信号は、処理上の問題から、8ビットデータを10ビットで置換して伝送するために起こります。(8b10bコード変換)
このため、10ビットなのに、8ビット(1バイト)分しかないのです。つまり、1500Mbit/s = 150MB/s、となります。(恥ずかしながら、筆者も長いこと勘違いしてました。)
さて、さらによく誤解の起きるハードディスクの転送速度ですが、これまで上に書きましたのは、あくまで外部転送速度、つまり、接続部のインターフェース回路の速度です。
これは、実際のHDD転送速度である内部転送速度:内部トランスファレート(TransferRate)より、ずっと上に置かれています。つまり上限値という表現が分かりやすいのです。
上限値外部転送速度の表現が、実際のHDD転送速度を表わしているかのように、ショップなどでも使われ、売られてるのは、大変残念なことです。
実際のHDD転送速度である内部転送速度は、現在でも、90-100MB/sec程度です。S−ATA2方式の、ATA300(300MB/s)どころか、従来のパラレル方式の、ATA133規格(133MB/s)よりも、遅いところにあります。
(もちろん技術的には、もうすぐ、133MB/sを超える時代が来るので、S−ATA方式が登場した訳ですが。)
【 S−ATA2 】:
これは、次のページで解説します。→S−ATA2の拡張機能
★HDD(ハードディスク)安価販売店(価格.COM 調べ)★
| パソコン工房 HDDページ | ツクモ
|
フェイスインターネットショップ |
2007年2月記
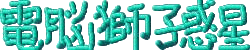

 ご意見、ご要望について
ご意見、ご要望について