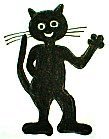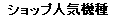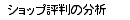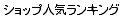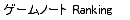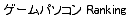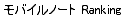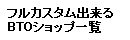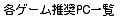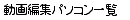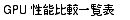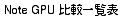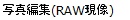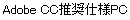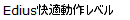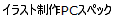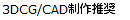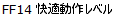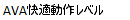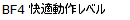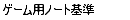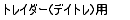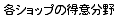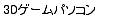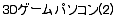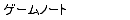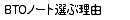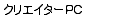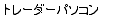ウルトラブック(Ultrabook)のコンセプト
(本ページはプロモーションが含まれています)
【関連深いページ】 : 高性能モバイルノート ランキング TOP 10へ
高性能モバイルノート ランキング TOP 10へ
たいていの人なら、インテルの提唱する「ウルトラブック(Ultrabook)」は、明らかに、アップルの「iPad やMacBook Air など、新しいブランドの薄型PC」に対抗するための概念であることに気づいています。
2011年の9月、インテル副社長ムーリー・エデン氏が、「Intel Developer Forum 2011 San Francisco」で、「ウルトラブック(Ultrabook)」について、その時代的位置付けや背景を述べました。
ノートPCは、過去20年の間に2度、大きな転換点を迎えて来たと言い、それは、
1.MMX Pentium(1995年、企業用途主体から個人用としても普及)
2.Centrino(2003年、セントリーノが登場。デスクトップPCからノートPCへの転換)
3.3回目が、今回のウルトラブック(Ultrabook)の登場
今回のウルトラブックが、第3の転換点であると位置付けました。
【ウルトラブックのコンセプト】
もちろん、ウルトラブック(Ultrabook)は、インテルが提唱の「薄型軽量ノートパソコンのカテゴリ」です。
しかし、インテルが目指すUltrabookは、ただ、「薄くて軽い」だけではない。次のような6つの要素を満たした製品であるべきだとしました。
■手軽にコンテンツを作れる →長い文章の記事を制作・編集できる(タブレット端末との差別化となる)
■使いたいときにすぐに使える →身近に置け、持ち運びしやすい(モバイル性)
■安心して使える
■自分好みに使える
■いつでも使える →身近に置け、持ち運びしやすい(モバイル性)
■入手しやすい価格である
インテルは、この「6つの要素」を実現するためには、次の条件が重要であると語りました。
■パフォーマンス
■応答性
■セキュリティ保護機能
■魅力的なフォームファクタ
■省電力性とバッテリ駆動時間
■エコシステムとコスト
ウルトラブックのコンセプトを具体化する「6つの要素」ということなのですが、これらの項目は、いつの世代のPCでも言われていることと同じであり、抽象的で分かりにくいと思われます。
唯一、■魅力的なフォームファクタの「フォーム」が、その薄さの形状のことを言っているのなら、少し真新しいのですが、これこそがアップルのMacBook Air などの後追いの印象を与えてしまいます。
パソコンの古い時代のことを思い返して見れば、「マウス」や「Windows」自体がアップル社の後追いだった訳で、別に今に始まったことではありません。(もっとも「マウス」はアップルの創作発明ではなく、某大手メーカーの試作品をまねたものですが。)
インテルやマイクロソフトに限らず、IBMの PC/ATから始まったDOSVパソコン自体がアップル(マッキントッシュ)を後追いして、追い越してしまうと言う歴史の中で進化して来たのであり、今また、新しい歴史の始まりであることは確かでしょう。
今後のウルトラブックの進化・進展で過去のように、アップルを追い抜けるかもしれないという期待もありますが、現時点では、かなり厳しいように感じます。
さて、上の「抽象的で分かりにくい」コンセプトは、すでに具体化されていますので、ここで、インテル社のウルトラブックの定義を書いておきます。
【ウルトラブックの定義】
●CPUは第2世代以降の Core i シリーズ(Sandy Bridge、Ivy Bridge 及び今後の Haswell)搭載。
●厚さ(高さ)は14型以上の場合は21mm以下、14型未満の場合は18mm以下。
(基本的に、光学ドライブはなし。)
●バッテリー駆動時間は5時間以上。8時間以上が奨励。
●入出力は Wi-Fi 機能のみが必須。Ivy Bridge 世代以降は、さらにUSB 3.0 対応。
●ラピッド・スタート・テクノロジーの搭載によるハイバネーション状態(パソコンの休止状態)からの7秒以内の復帰の実現。
●スマート・コネクト・テクノロジー搭載。(Ivy Bridge 世代以降搭載モデル)
(Intel スマート・コネクト・テクノロジーとは、コンテンツを常に最新状態に保つために、システムがスリープ中でも、電子メール、お気に入りのアプリ、ソーシャルネットワークを継続的に自動更新する機能)
さて、ウルトラブック仕様を謳うノートPCは、2011年秋頃から発売されています。
しかし、CPUには、第3世代のCore i シリーズ「Ivy Bridge」が間に合わなかったために、第2世代のシリーズである「Sandy Bridge」を採用していました。
しかし、2012年4月に、第3世代のCore i シリーズIvy Bridgeが発売されるに至り、2012年半ばに、このIvy Bridgeを搭載したノートPC製品が多数発売されて来ています。
(つまり、2011年のフォーラムでは、ウルトラブックのコンセプトを満たす最初の製品が第3世代のCPU「Ivy Bridge」であるとしていたのですが、経過的に「Sandy Bridge」で代用していたということになります。)
今後は、ウルトラブックへの最適化がされたプロセッサとされる、「Haswell」を搭載の仕様が見込まれているようです。
これは、さらに、消費電力を現行製品の約半分に低減し、ノートパソコンにおける熱設計問題を改善するとされています。もし、これが実現すれば、素晴らしいことです。
なにしろ、PC自作派の人なら解り易いのですが、
ノートPCを、さらに「薄く軽くする」ことは、ますます高性能・高速化するために、発熱量を増やさざるを得ないCPUを冷却するファンやヒートパイプ式のクーラーを頭に載せなければならないCPU本体を改良進化させることと、ほぼ同義なこととなるためです。
(以上、一部の情報は、ウィキペディアのUltrabookから、参考にしています。)
【話題のウルトラブック例】
 NECの「LaVie G タイプZ」(8月23日発売):厚さ14.9mm、875g。→
NECの「LaVie G タイプZ」(8月23日発売):厚さ14.9mm、875g。→LAVIE Direct HZ(新製品:2 in 1ノート)驚く軽さのウルトラブック約875gの13.3型
 ソニー「VAIO T」シリーズ(6月9日発売):
ソニー「VAIO T」シリーズ(6月9日発売):
●13.3型が、厚さ17.8mm、約1.5kg(最軽量値で)。→VAIO Tシリーズ13
●11.6型は、厚さ17.8mm、約1.32kg(最軽量値で)。→VAIO Tシリーズ11
 富士通の14型ライフブック「LIFEBOOK UH75/HN」(6月7日発売):厚さ9.0〜15.6mm、約1.44kg。→LIFEBOOK UH75/HN
富士通の14型ライフブック「LIFEBOOK UH75/HN」(6月7日発売):厚さ9.0〜15.6mm、約1.44kg。→LIFEBOOK UH75/HN
 デル・コンピュータの14型「XPS 14」プレミアムモデル(6月26日発売):厚さ20.7mm、約2.1kg。→XPS14 Ultrabook
デル・コンピュータの14型「XPS 14」プレミアムモデル(6月26日発売):厚さ20.7mm、約2.1kg。→XPS14 Ultrabook
【関連記事のページ】 :
 同上の国内3機種とMacBook Airを比較→この夏発売、人気のウルトラブック3機種を比較評価レビューへ
同上の国内3機種とMacBook Airを比較→この夏発売、人気のウルトラブック3機種を比較評価レビューへ
2012年9月修正記
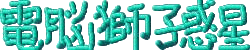


 ご意見、ご要望について
ご意見、ご要望について