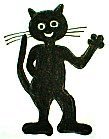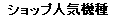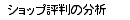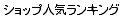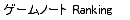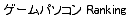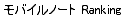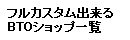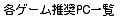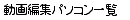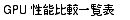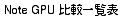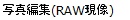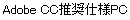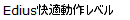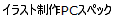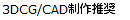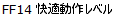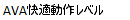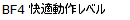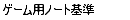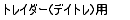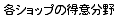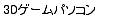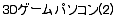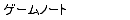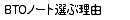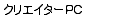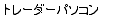初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR3
(本ページはプロモーションが含まれています)
【 DDR3L とは?】の記事をページの最下段に追加しました。(2024年2月追記)
【 本ページと最も関連の深いページ】 :
 初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR4
初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR4
 初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR5
初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR5
BTOパソコンのメモリーは、自分の用途に見合った容量(サイズ)と速度を選べばよいのですが、Windows 7 になってから、1GB以上、Windows Vista では、Home Basic で、512MB以上、Home Premium, Business 版より上のクラスですと、1GB以上がマイクロソフトの推奨(最低動作容量)なったため、推奨の2倍のだいたい、1GB〜2GB程度を選ぶ方が多いようです。
本ページは、2007年から発売が始まった、DDR3−SDRAMの解説です。このタイプは現在では、主流のメモリーになったようです。
発売当初は、主に自作BTOパソコン系列のヘビーユーザー、ゲーマーや特定ニーズ向けPCから使われ始めました。
また現在、DDR3-1066(PC3-8500)、DDR3-1333(PC3-10600)、DDR3-1600(PC3-12800) がかなり流通しており、DDR3-2200(PC3-17600)が'09年9月に、DDR3-2300、DDR3-2400(PC3-19200)、が'10年1月から発売されたようです。
【 DDR3:第3世代DDRメモリー 】:
正式には、DDR3−SDRAMで、これは、ダブル・データ・レート3−同期式DRAM(Double-Data-Rate3 Synchronous Dynamic Random Access Memory)の略です。
外観は、従来品と同じですが、動作電圧が、DDR2 の1.8Vに対し、さらに下げられ、1.5V となりました。ピン数は、DDR2 と同じで240Pin、スロットの切り欠き溝も1つですが、DDR2 とは位置をずらして、誤挿入防止しています。
DDR2より、2倍に高速化されました。これは、従来4ビットだった、プリフェッチ機能(CPUのために、あらかじめ先読み取り出し準備)を、2倍の8ビットに拡張したもので、動作原理は従来から同じです。
(PR)総アイテム2000台!即日発送リフレッシュPC
つまり、クロック信号の立ち上がり時と立ち下がり時の 両方(ダブル・データ・レート、DDR)で、データの読み書きが行なえるようにしたモードで動作します。この速度をデータ転送レート(Mbpsという単位。※注記)と言いますが、この数字の2分の1が、メモリーモジュールのバスクロック周波数(Frequency)(単位ヘルツ:Hz)となります。
このDDR3メモリーの内部セル周波数は、外部データ転送レート(Mbps)の8分の1で動作していて、従来のメモリーより少し速くなった程度(DDR2とは同じ)で、ほとんど変わりません。(バスクロック周波数の4分の1です。)このため、高速化されながらチップの発熱が低く抑えられ、効率がいいのです。
つまり、
DDR3規格が「DDR3-1333」のメモリーでは、外部データ転送レートが、1333Mbpsを指し、その 1/2 の、667MHzが、メモリーバスクロック周波数となり、さらに 667MHz/4 の 166MHzが、内部セル周波数ということになります。
※注記)外部データ転送レート(bps)については、DDR〜DDR2の頃まで、(実際は2分の1である)バス周波数(Hz)と(同義語で)使用していた場合があり、当サイトでもDDR2まで、外部周波数(Hz)と表記していました。今回から正確な(bps(bit per second))表現に変更しました。また、インテルCore i7 920などで使われる、QPI = 4.8GT/s=4.8 GigaTransfers per Second、という表記もあり、バスやチャンネル速度の場合には同義語的に使われるようです。
アマゾンなどでは、今でも、DDR3-1600MHzなどの、商品呼称で販売されているのは、この理由からだと思われます。実に紛らわしいですねー。(DDR3-1600Mbps と表記してほしい。)
さて、DDR3メモリーの種類とその表記ですが、
| メモリー規格 | データ転送レート (Mbps) |
帯域幅:データ転送速度 (MB/sec) 1channel当り |
バスクロック周波数 Frequency(MHz) |
内部セル周波数 Frequency(MHz) |
|---|---|---|---|---|
| DDR3-2400(PC3-19200) | 2400 | 19200(19.2GB/s) | 1200 | 300 |
| DDR3-2300(PC3-18400) | 2300 | 18400(18.4GB/s) | 1150 | 287.5 |
| DDR3-2200(PC3-17600) | 2200 | 17600(17.6GB/s) | 1100 | 275 |
| DDR3-1600(PC3-12800) | 1600 | 12800(12.8GB/s) | 800 | 200 |
| DDR3-1333(PC3-10600) | 1333 | 10600(10.6GB/s) | 667 | 166 |
| DDR3-1066(PC3-8500) | 1066 | 8500(8.5GB/s) | 533 | 133 |
| DDR3-800(PC3-6400) | 800 | 6400(6.4GB/s) | 400 | 100 |
![]() アマゾンでメモリーDDR3の価格を調べる。→例:DDR3-1333(PC3-10600)
アマゾンでメモリーDDR3の価格を調べる。→例:DDR3-1333(PC3-10600)
上の表で、カッコ内に書いた、PC3-12800とかの数字は、メモリー帯域幅(※注記2)を表す 12800(12.8GB/s)、 というデータ転送速度のことで、表示の数字がそのまま、メモリーの速度性能を表わすので、最近使われるようになったようです。
速度性能の比較をする場合は、外部データ転送レート(Mbps)やバスクロック周波数(MHz)よりも、この GB/Secという、データ転送速度を使うと評価しやすいのです。この表示方式であれば、メモリーの接続先である、各種のデータバス転送速度と(6.4GB/Secなどで動作してる場合)、速度上の整合性が取れているかが、すぐに分かります。
接続先のどこかで、データ転送速度の低いもの(デバイス)があれば、ボトルネックが起こります。
また、表中のメモリー帯域幅は、1枚(single channel) の時です。DDR3メモリーは、通常2枚 (dual channel) か3枚(triple channel)で使われ、この時の帯域幅は、(バス幅が2倍、3倍となりますので、)それぞれ2倍、3倍に広がります。ただ、ピークの帯域幅ということであり、実測値はこれ以下ということです。
ピークの帯域幅の例:
PC3-10600 (1枚) 10.6 GB/s
PC3-10600 (2枚) 21.2 GB/s
PC3-10600 (3枚) 31.8 GB/s
【 デュアル・チャンネル (dual channel) 】:
DDRメモリーは、通常、デュアル・チャンネルで使用します。2チャンネルで使う、つまりペアで、2枚組(メモリースロットに取付ける)するとデータ長が増し、さらに2倍高速化されます。
【 シングル・チャンネル(single channel) 】:
DDRタイプのメモリーを1枚で使う時のデュアル・チャンネルに比較する時の言い方で、メモリー速度がデュアルより遅くなります。(デュアル・チャンネル方式が登場した時、従来方式をこう区別したということです。)
【 トリプル・チャンネル(triple channel) 】:
新しいネイティブ・クアッドコアCPUである、Core i7 対応マザーボード(Intel X58 Expressチップセット採用)から、3枚組(3枚刺し)で取付けるトリプル・チャンネル仕様のものが登場しました。
このタイプのマザーは、6個のメモリースロットが用意されているものが多いようですが、DDR3タイプのメモリーしか使えません。またインテル独自のオーバクロック規格である「XMP」に対応してる必要がありそうです。
【 DDR3L とは?】
DDR3の低電圧版(Double Data Rate 3 Low voltage)です。2012年頃からDDR3に代わり、2016年頃まで主流になったようです。
通常のDDR3が、1.5V駆動なのに対し、DDR3Lは、1.35Vで駆動します。電圧が低い分だけ消費電力を抑えることができます。
その他の仕様や規格は、上に書いたDDR3-SDRAMと同じようです。
しかし、第4世代 intel CPU(Core i5 -4xxx etc)から、DDR3は、互換性がなくなりました(10月/2014年くらい)。
この第4世代CPUは、メモリーの1.35 V動作のみをサポートするようになったのです。
現在(2024年2月)も売られている DDR3L メモリーは、ノート用SO-DIMMが中心となったようです。(1.35V - 1.5V 両対応も販売)
(DDR3L メモリー販売例)
Transcend ノートPC用メモリ DDR3L-1600(PC3L-12800) 8GB 1.35V (低電圧) - 1.5V 両対応 204pin SO-DIMM
【 本ページと最も関連の深いページ】
 初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR4
初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR4
 初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR5
初心者にやさしいメモリーの知識・解説−DDR5
2010年1月追記、修正
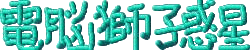



 ご意見、ご要望について
ご意見、ご要望について